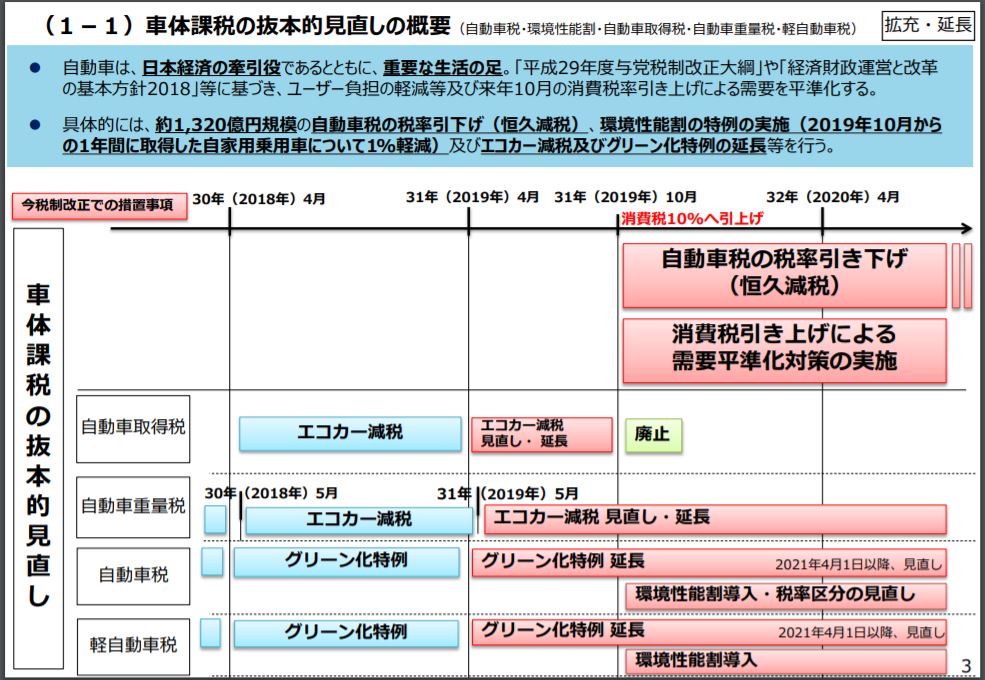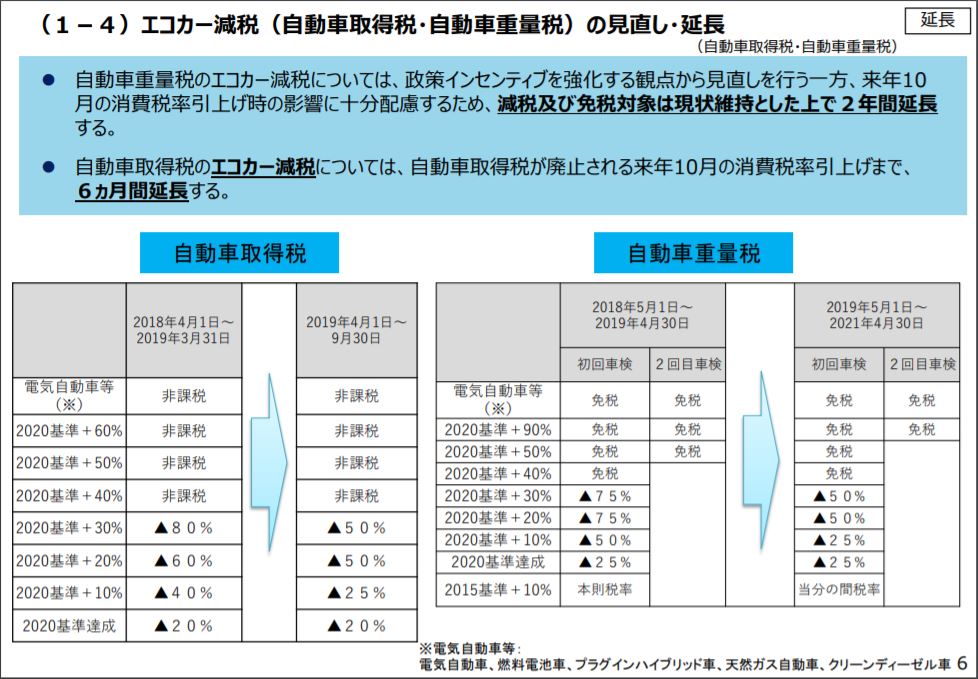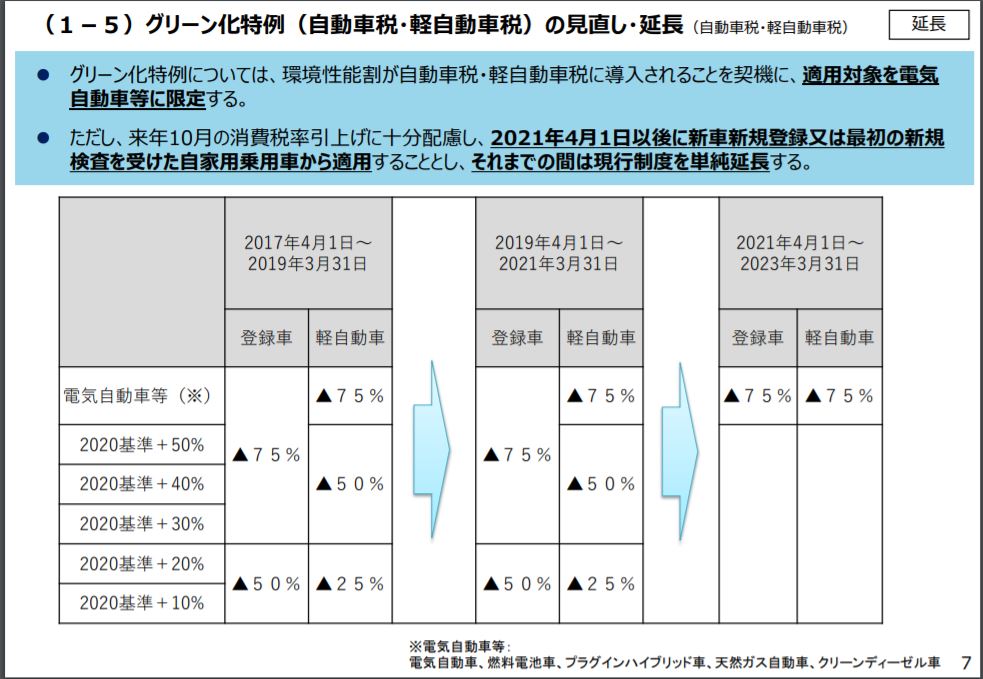中古で購入して早2年、購入当初は現在地がわかればいいやと思っていたナビゲーションでしたが、やはり地図が古くなってきて、ルート検索にも問題が出てくるようになると新しいものが欲しくなります。既に11年目に突入で、走行距離も10.8万㎞ですが、最新のナビを取り付けることにしました。
 2年間使用したユピテルのナビYPL522。目的地を電話番号や登録されているデータから設定しているのに、目的地設定が行えない時がある。圏央道が伸びたりきたせんが出来たり、地図も古いので更改することに。値段相応の機能としては十分だったと思います。確か1.2万くらいだったように記憶しています。
2年間使用したユピテルのナビYPL522。目的地を電話番号や登録されているデータから設定しているのに、目的地設定が行えない時がある。圏央道が伸びたりきたせんが出来たり、地図も古いので更改することに。値段相応の機能としては十分だったと思います。確か1.2万くらいだったように記憶しています。
 ユピテルの取り付けに使用していた、自作のL字型ステー。このねじ穴を利用してゴリラを取り付けたい。
ユピテルの取り付けに使用していた、自作のL字型ステー。このねじ穴を利用してゴリラを取り付けたい。
本体の固定
取付は、ユピテル YPL522の取付時に自作したステーをそのまま利用します。ステーのねじ穴を利用したいので、ゴリラをカメラねじを使って取付できるようにするアダプター、REC-MOUNTS ナビマウントヘッドパーツ[HED-A-CN] を購入しました。


REC-MOUNTS のナビマウント。ゴリラの取り付けに合う構造となっています。

REC-MOUNTS ナビマウントヘッドパーツ[HED-A-CN] の裏側。こんな感じでカメラねじが使用できるミリねじ規格のねじがあります。ねじも付属かと思ったらありませんでした。
調べた限り、ゴリラをねじ穴で固定する場合は、この方法しかありませんでした。
取り付け角度の調整ができないので、L字ステーの取り付け部分を垂直に起こします。
 ステーの角度を調整。調整は、ステーを万力で挟み、ハンマーでたたきます。
ステーの角度を調整。調整は、ステーを万力で挟み、ハンマーでたたきます。
アダプターはカメラ台のねじを使用します。100均一でプラスチックのカメラ台を購入し、ねじ部分だけ使ってみました。ねじだけでは接続が弱いので、自動車用の強力両面テープを併用します。
 100均で購入したカメラの三脚のねじ部分だけ利用しました。ねじがプラスチックなので、金属製のものに変えようと思います。
100均で購入したカメラの三脚のねじ部分だけ利用しました。ねじがプラスチックなので、金属製のものに変えようと思います。
7インチということで、重さが気になりましたが、踏切を渡ってみても特にぐらつくことが無かったので大丈夫そうです。このエアコン吹き出し口、挿入して固定してあるだけですが、結構しっかりしている様子。
タッチパネルの操作で、若干本体が動く感じがしますが、大きく揺れることは無いので良しとしました。
電源
電源は、付属のシガーソケットを利用する電源アダプターを使います。ヒューズボックスから引いた12V電源とアースの配線を電源アダプターへ接続します。電源アダプターはグローブボックス裏にタイラップで縛り付け固定します。これで配線はすっきり。
 シガーソケット電源アダプタから電線を引っ張り、ヒューズボックスから取った電源と接続します。
シガーソケット電源アダプタから電線を引っ張り、ヒューズボックスから取った電源と接続します。
VICSアンテナ
Aピラーカバーはドライブレコーダーの取り付けの時に外しているので、外し方は問題ありませんでした。ピラー上部のAIRBAGと書いてあるプラスチックのカバーを取り外すと、中にトルクスねじが見えます。フロントウィンドウが近いのでユニバーサルジョイントを使用してドライバーとトルクスビットでねじを緩めます。
 フロントウィンドウが近いので、ユニバーサルジョイントが必要
フロントウィンドウが近いので、ユニバーサルジョイントが必要
パーキングブレーキセンサーアダプタ
停車通以外にもナビの操作をしたいので、パーキングブレーキの信号入力を短絡させました。専用のプラグも販売されているようですが、要は短絡させればよいので、1㎜のはんだを4つ折りにしてねじ込み、問題なく走行中でもナビの操作ができるようになりました。TVも見られるようになりますが、TVは見ないのであまり関係ないかな。
後日追記
走行中に、ナビが走行中と認識したようで、突然ナビ操作ができなくなりました。導電体をパーキングブレーキのプラグ穴に入れるという方法は今一つかもしれません。確実に、こういったプラグを購入するのが良さそうです。
若干の問題
車内で作業をしていたら、荷物を持ち上げた拍子にオーバーヘッドコンソールのプラスチックカバーに腕が当たってしまい、パリンとかけてしまいました。
 このプラスチックカバーですが、とても脆くなっています。もうバキバキです。。。
このプラスチックカバーですが、とても脆くなっています。もうバキバキです。。。
この部品は購入当初から、固定部分が割れ、両面テープやホットボンドなど、いろいろ手を尽くしてやっと固定できた部品です。メッシュ部分が割れただけなので目立たないように裏にスポンジのテープを張り付け良しとしました。あまりこだわっては居られません。
完成!
7インチで見やすいし、やはりナビはそれなりに良いモノじゃないと、運転していてストレスが溜まります。動作も早いし、ルートまずまず。交換してよかったです。
 操作時に少しぐらつきますが、走行時は安定しています。
操作時に少しぐらつきますが、走行時は安定しています。