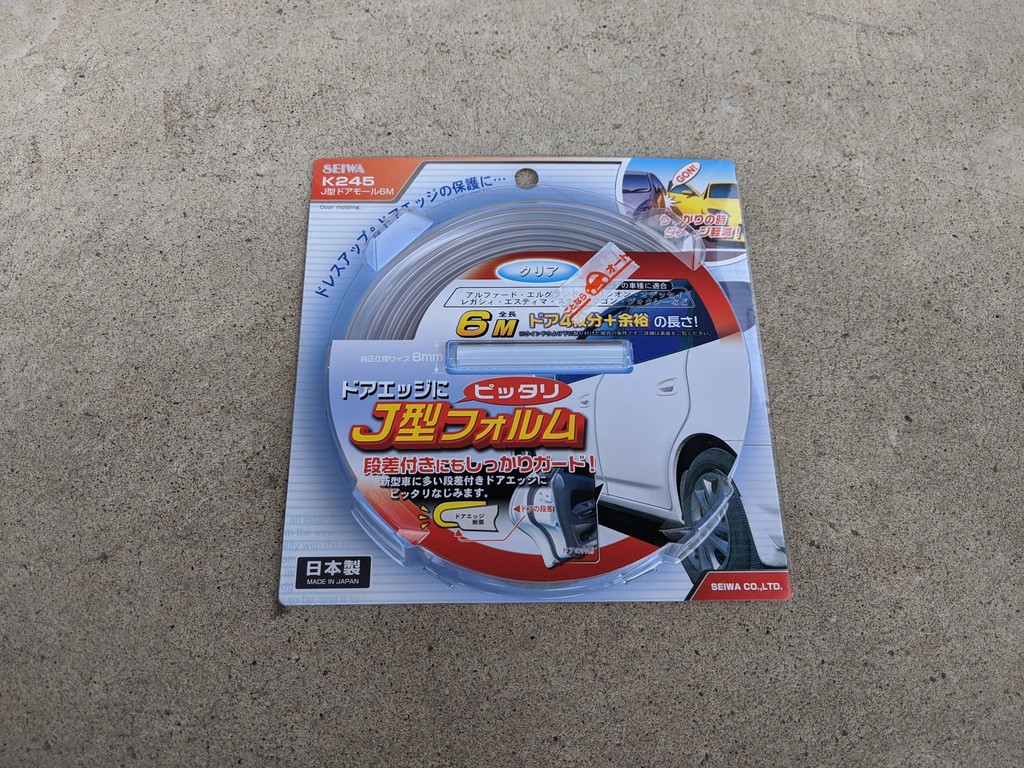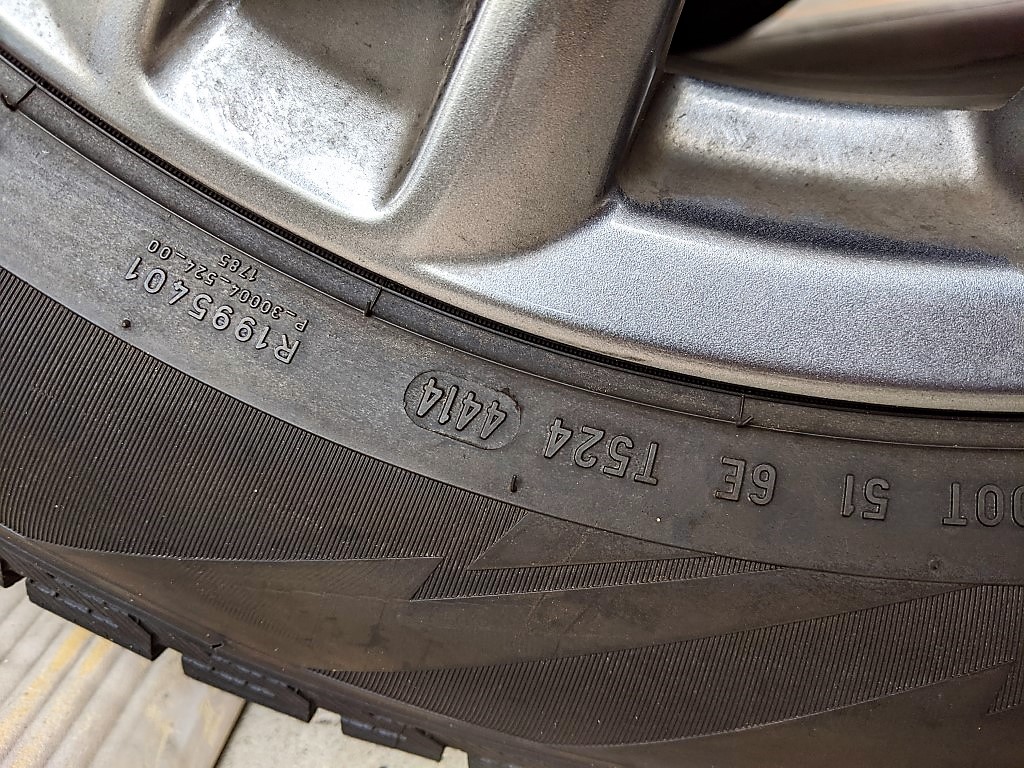走行距離
距離は4,000kmちょっと。距離は全く伸びていない。その理由の一つが、11月まで、前の車であるノアを保有していた事で、北海道旅行はCX-8ではなく、ノアで行った事。私としては、一度九州まで無給油走行することをやってみたいのだが、いつ実現することやら。
積載性
キャンプ道具を積むと、積載がCX-8の場合は足りない。かといって、ルーフボックス(THULE XT XLサイズ)を装着すると、全高が2.3mほどになり駐車に気を遣うようになってしまう。
ロードバイクを前後のタイヤを外しても簡単には縦に積めなかったのは大きな誤算。できるだけサドルの位置はずらしたくないので、そうなるとフォークを2列目と3列目シートの間に落とさなければならず、積み込みと積み出しにテクニックが必要となる。
燃費性能
距離がたかだか4,000kmほどなので、そう気にしたことも無いのだが、高速道路をおとなしく走ると16㎞/Lほどになる。ちょっと飛ばしても燃費が落ちないのはうれしい。
街中は恐らく12~13㎞/L。サイズと重量を思えば十分な数値だけど、欲を言うともう少し伸びてほしい。
スタイリング
いまだ大いに気に入っている
走行性能
12月と1月にちょっとだけスタッドレスタイヤで雪山を走行するときがあった。徐々にペースを上げてみたが、緊張するようなシーンに合うことは無く、終始安定した走りに大いに満足。また、キャンプで結構な山道を登るときも、低速からグイグイ加速する感じが病みつきになる。
インテリア
評判が悪い純正のSDメモリナビだが、それほど悪いとは感じない。ただ、距離が短い道を優先する傾向が強く、例えば国道と並走する旧道がある場合など、一度旧道を経由させてまた国道へ戻るルートを案内したりする。また、国道でとても右折は無理な場所なのに、目的地が反対車線とか。
コマンドコントロールが車体と一体となって、操作性は慣れれば相当に良いだけに残念といえば残念だが、今のところ致命的に困ったことは無い。
3列シート
3列目に人が乗ることは一度もなかった。
結論
総合評価としては、5点満点中3.8点くらいかと。
積載性だけが大きく期待に届いていないが、他はおおむね満足。積載性はどうしようもないので、荷物を見直す方向で考えるしかないか。
自分にぴったし合うのは、CX-5のストレッチバージョン、もしくはCX-8の2列シート5人乗りかもしれない(存在しないけど)。5人乗車でラゲッジスペースが拡大され、低床化が図られればなと思う。